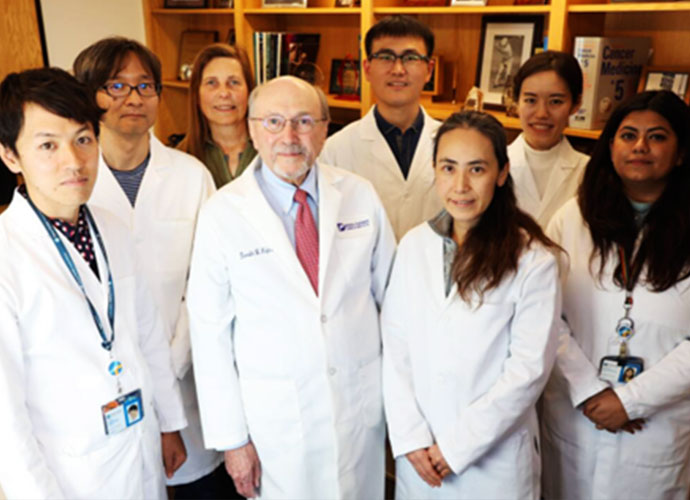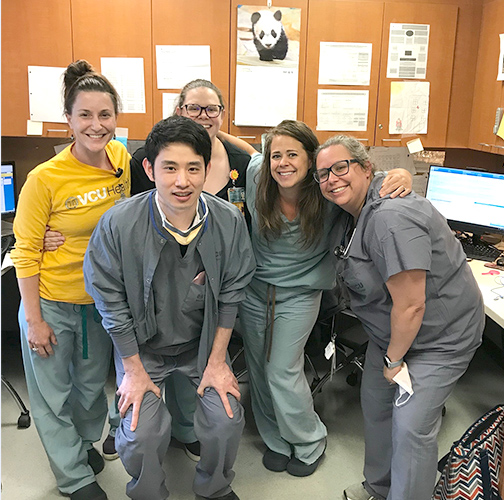留学レポート
REPORT 01
原武 直紀Naoki Haratake
(入局年/平成25年)
ハーバード大学ダナ・ファーバー癌研究所
2022年5月より米国のボストンにあるハーバード大学ダナ・ファーバー癌研究所で、ポスドクとして勤務しています。現在、肺癌の分子標的薬の耐性機序について研究を進めています。
日々、臨床や手術に携わる中で、癌の知識を根本から身につけ、世界中のオンコロジストとdiscussionができるようになりたいという思いが強くなり、海外基礎研究の世界に飛び込みました。渡米してすぐは英語がわからないのか、研究がわからないのかすらわからない苦しい状況でしたが、ただ必死に研究を進める中で約1年が過ぎ、気がつけばボスとの数時間のdiscussionを毎週繰り返しており、当初の目標は少しずつ達成されていることを実感しています。世界的な施設でP.I.を務めるボスの癌全体にわたる凄まじい知識や発想、そして意思を尊重してくれる指導法には感銘を受けるばかりです。
また、ボストン は世界的なラボが近くに多く、コラボレーションの垣根も低く、著名な研究者たちとのmeetingも非常に貴重な経験となっています。ボスを含め、世界には本当にとんでもなく頭の良い人がいるものだとしみじみ実感します。一方で妻も子供達もとてもこちらでの生活、学校を楽しんでおり、家族共々大変貴重な経験ができています。自分と似た境遇、志をもつ人たちとの出会いも多く、それだけでも留学の価値があると感じます。自分で行き先を選び海外での生活を経験できる職種も限られているかと思います。長い医師人生、ぜひ将来の海外留学も視野に入れてみてください。
REPORT 02
今井 大祐Daisuke Imai
(入局年/平成24年)
バージニア州立大学
私は2019年よりアメリカのバージニア州にあるバージニア州立大学で、腹部多臓器移植のクリニカルフェローとして勤務しています。こちらではドナーやレシピエントの手術に加え、移植の適応評価、ICUを含めた患者管理なども行っています。
アメリカの臨床プログラムに参加する利点として、圧倒的な症例数から得られる経験は代え難いものがあり、さらに免疫抑制剤の使い方や移植臓器の機械還流など最先端の技術も学ぶことができます。
移植外科は欧米で始まった脳死移植を中心に発展しており、肝移植について言えば、欧米から始まった脳死肝移植から、アジアで生体肝移植が発展し、成熟期を迎えています。現在、欧米では生体肝移植の必要性が高まっており、生体肝移植のプログラムを立ち上げるためにアジアから多くの医師が訪れており、有用な人材として求められています。
現在、アメリカではクリーブランドクリニックの橋元先輩、マウントサイナイの別城先輩が移植外科医として活躍されており、その他にも多くの日本人の先生がアメリカで移植外科医として活躍されています。消化器・総合外科での手術技術や術後管理の経験を基礎として、さらに自分の力を伸ばす大きなチャンスであり、また、その技術を世界に伝えることができたら素晴らしいと思います。是非一緒に頑張りましょう。
REPORT 03
橋元 宏治Koji Hashimoto
(入局年/平成7年)
クリーブランドクリニック
私はアメリカのオハイオ州にあるクリーブランドクリニックで、腹部多臓器移植のクリニカルフェローとして勤務しています。こちらではドナーやレシピエントの手術に加え、移植の適応評価、ICUを含めた患者管理などのトレーニング中です。アメリカの臨床プログラムに参加する利点は、短期間に圧倒的な症例数を経験出来ること、世界中から集まってくる仲間と競い合えることだと思います。
クリニカルフェローシップは、レジデントを終えた医師が自分の専門分野をより深く掘り下げて行くためのトレーニングプログラムです。移植外科では昼夜を問わず手術があるため時間に追われる毎日です。肉体的精神的にタフであることが要求されますが、とてもやりがいがあります。医学部の学生の方、また卒後間もない方の中にはアメリカの医師免許取得を目指して頑張っている方が多くいると思います。決して平坦な道ではありませんが、努力する価値は十分あります。日本での経験を基礎に、自分の力を伸ばす大きなチャンスにめぐりあうことが出来ると思います。
REPORT 04
川原 尚行Naoyuki Kawahara
(入局年/平成4年)
NPO ROCINANTES
今の時代は恐ろしいくらいの速さで展開していっています。この変わりゆく時代の中で、不変のものが根底にあるこの教室こそ、次世代に誇れるものにならなければと思います。
私は、平成4年に当教室に入局し、大学院を経て外務省に入省しました。海外に身を置いて10年以上経ちました。
今はアフリカ・スーダンでNPOを設立し医療活動を行っています。スーダンは内戦が続き、現在でも紛争のある国です。日本とは全く異なる環境下にあって、医療のみの活動に留まりません。水・衛生問題、保健教育、学校教育、産業育成など多岐に構想は広がります。また、九州大学とスーダンの研究所との学術協定も締結されました。政治的、宗教的なものを乗り越えて、学術交流が成功することに尽力しています。
私は年に2回ほど帰国し、教室に顔を出します。私の身分は留学生となっており、赤で表示されています。そして、在籍を示す白に反転させます。年に2度の反転です。これが私の身の拠り所であり、教室員が頑張っていることが、海外での私の励みにもなります。これが、教室の本当の良き伝統になっているのでしょう。
この伝統を守り、そして新しきものへと発展させていく気概も持って、将来を見つめてください。